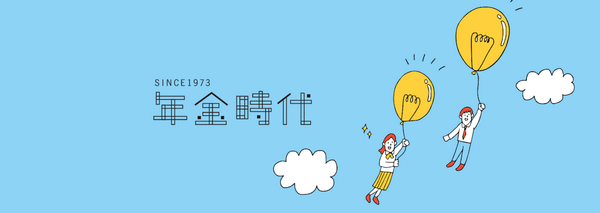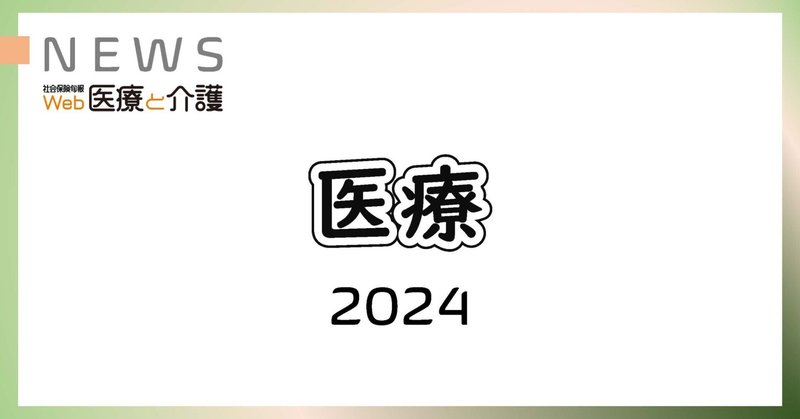最近の記事
- 固定された記事
マガジン
記事

マイナ保険証でオン資確認できない場合、紙の保険証の提示なくても3割等の自己負担割合――厚労省がセミナーで再周知(2024年7月19日)
厚労省は7月19日、「徹底解決!マイナ保険証への医療現場の疑問 解消セミナー」をオンラインで開催した。マイナ保険証持参患者については、マイナンバーカードでオンライン資格確認ができず、紙の保険証の提示がない場合であっても、3割等の適切な自己負担割合での支払いを求めることを医療機関等に再周知した。また、電子証明書の有効期間切れ後の特例措置についても説明した。 被保険者等がマイナ保険証を持参した場合は原則10割負担としない――こうした窓口での取扱いについて、厚労省は令和5年7月1