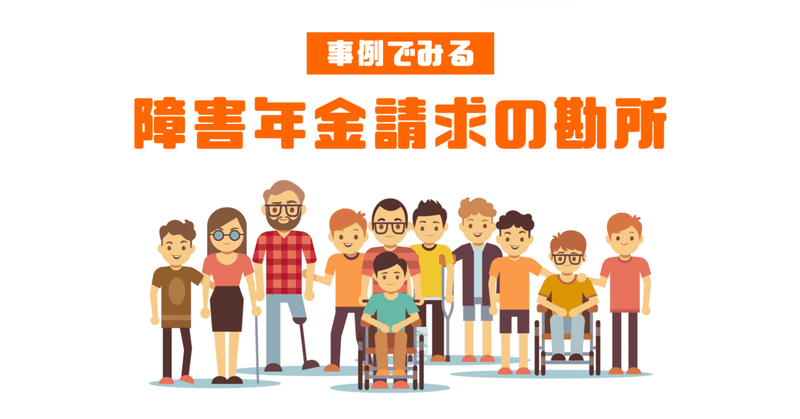
#12 障害年金と加給年金
障害年金には加給年金というものがあります。これは老齢年金にもある制度で、要件に該当する配偶者や子が受給者にいた場合、本来の年金額に加えて支給されるものです。いわゆる扶養手当のようなものですが、一般的な扶養とは概念が異なりますのでご注意ください。
加給年金を受給する場合は、要件に該当する配偶者や子がいることを証明する必要があります。しかし、障害年金に加算される加給年金は、老齢年金に加算される加給年金とは仕組みが少々異なり複雑であることから、適切な証明を取得することが難儀な場合も多く、障害年金の手続きが滞ることも少なくありません。
今回は、この加給年金について注目し、事例を検証していきたいと思います。
1.加給年金とは
加給年金には、配偶者がいることにより加算される「配偶者加給年金」と、年齢要件を満たした子がいることによる「子の加算」があります。加算の対象となる配偶者及び子の要件は、図1のとおりです。

図1のように、配偶者加給年金は障害厚生年金2級以上の時に加算されます。子の加算は障害基礎年金に加算されます。障害厚生年金2級以上ですと、障害基礎年金も同時に受給できますので、配偶者加給年金と子の加算も同時に受給できますが、障害基礎年金のみですと、要件を満たした配偶者がいたとしても、配偶者加給年金は支給されません。
各要件に求められる主な証明は次のとおりです。
①戸籍謄本(婚姻及び子の関係を証明)
②世帯全員の住民票(生計同一関係の証明)
③課税(非課税)証明等(年収850万円以上ないことの証明)
※②と③はマイナンバーによって添付を省略することができます。
生計同一関係は、基本的に同居していることが求められますが、別居していても同居しているのと同様の暮らしをしていた場合は、それを第三者に証明してもらうことで、生計同一関係を成立させることもできます。
加給年金を請求するタイミングは、いつ配偶者や子がいたかによって異なります。障害年金の受給権発生時に要件を満たした配偶者や子がいた場合は、障害年金請求時に同時にします。この段階ではまだ障害等級の認定審査前ですから、どの障害等級に認定されるかは不明なのですが、2級以上に認定された時に漏れなく加給年金が支給されるよう、認定結果にかかわらず対象となる配偶者や子がいた場合、加給年金の請求も同時に行います。
障害年金の請求書には、加給年金に関する記入欄がありますので、それに記入することで請求行為になります。逆に、障害年金の受給権発生後に要件を満たした配偶者や子ができた場合は、その都度、加給年金を請求するための書類「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(229-1)」を提出する必要があります。

以上のような説明ですと、そんなに複雑ではないように感じるかもしれませんが、この加給年金が障害年金請求にどのような影響を及ぼすか、具体的な事例をみていきましょう。

初診日は「平成29年6月9日」のK精神科となり、この時、厚生年金に加入していますので、障害厚生年金の請求が可能であることが分かると思います。また、初診から現在まで同じ医療機関にかかっていますので、初診証明は不要となります。
ここで問題になるのは、障害認定日で請求するか、それとも事後重症で請求するかという点です。「うつ病と診断されてから休職を繰り返す」とありますから、障害認定日時点で既に障害等級に該当するほどの症状である可能性があります。
しかし、障害認定日請求と事後重症請求では、請求に必要となる書類が加給年金の関係で大きく変わってしまうのが、今回の事例の勘所です。
ここから先は
¥ 100


