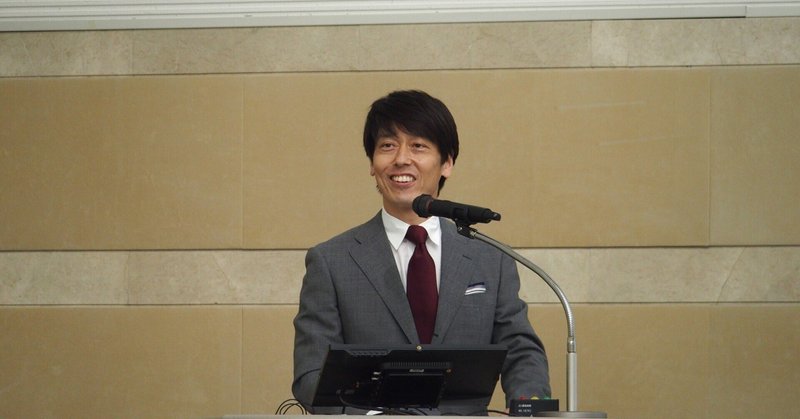
「自然に健康になれる環境づくり」をテーマに医療科学研究所がシンポジウムを開催(2023年9月15日)
医療科学研究所(江利川毅理事長)は9月15日、「『自然に健康になれる環境づくり』に向けたヘルスケア産業の変革―誰も取り残されないウェルビーイングの達成に向けて」をテーマにシンポジウムを開催した。
基調講演を行った近藤尚己京都大学大学院医学研究科主任教授は、健康格差への対策として社会的環境を整備することが重要であると指摘。さらに、将来世代の健康を守るために地球環境の問題にも取り組む必要があると問題提起した。これを受けたパネルディスカッションでは、社会的な環境整備として健康経営やPHRなどに関する取組みが報告された。自然環境に関しては、ヘルスケア産業が環境に与える影響や再生可能エネルギーを医薬品製造に活用する取組みが報告された。

内山審議官が医療DXを説明
江利川理事長は開会のあいさつにおいて、「高齢になっても健康で元気に生活できることを誰もが望んでいる。これには、環境の影響も大きい。例えば、高齢者が地域でボランティア活動やスポーツをしていると、認知症になる確率が低くなる。公共交通機関を使って結果的に歩く距離が長い高齢者は、心身の健康が長く続くという調査結果もある。自然に健康になれる環境は、工夫すればいろいろなところに作りうる」と述べた。

来賓としてあいさつした厚労省の内山博之医薬産業振興・医療情報審議官は、政府が現在力を入れている医療DXの取組みが「自然に健康になれる環境づくり」につながるとして、医療DXの進捗状況を報告した。

医療DXの狙いは、デジタル技術の活用により医療や介護、ヘルスケアのあり方自体を変革し、新たな価値を創造するものであると説明。例えば、保健・医療・介護のさまざまな情報が切れ目なく共有されるようになれば、自身の健康管理、健康づくりや疾病予防に生かせるようになる。また、適切なタイミングで、受診を促すことができるようになることも期待されるとした。
啓発だけでは格差広がる
近藤尚己京都大学大学院医学研究科主任教授は、環境とヘルスケア産業をテーマに講演した。健康には、個人の体質や生活習慣だけでなく、社会経済状況や社会的ネットワーク、生活環境や社会のあり様、文化・社会制度などの社会環境が影響すると説明。
近藤教授は、「健康について知識の啓発を行うだけでは、社会的に有利な方がすぐに行動を変えられる一方で、その余裕がない人は行動を変えられないため、健康格差が広がってしまう」と述べ、個人の行動変容を求める土台として社会環境の整備を行うことが重要であると強調。厚労省の健康日本21(第3次)では、社会環境の整備が今まで以上に重視されていると説明した。

健康を考えるに当たって、近藤教授は地球環境に目を向けることも重要であると指摘。「地球環境のリソースを費やして、いま生きている世代が健康になっても、将来世代が不健康になっては世代間健康格差が生じてしまう」と述べた。全産業の地球温暖化ガスの排出量のうち、医療産業の排出量は5%を占める。「これは決して小さいものではない。誰もが健康になれる持続可能な環境づくりのためには、地球環境の問題は避けて通れない。ヘルスケア産業が当事者として何をすべきかを考えていくべきだ」と問題提起した。
「健診戦」で行動変容に成功
パネルディスカッションでは、ヘルスケア産業や社会環境整備、地球環境への対応にかかわる5名の識者による発表が行われた。

経済産業省の橋本泰輔商務・サービスグループヘルスケア産業課長は、PHR(パーソナルヘルスレコード)に関する事業を説明した。現在、PHRについてはマイナポータルなどを経由した情報やライフログデータを掛け合わせたサービスを、日常生活や医療機関受診時に活用できるようにすることが期待されている。橋本課長は、今後、公的なインフラの制度整備に加えて、民間事業者と連携して環境整備を進め、さまざまなユースケースを創出するとの考えを示した。
株式会社ミナケアの山本雄士代表取締役社長は、健康経営の普及や、データヘルス計画の作成支援など、同社の企業の健康への投資を推進する取組みを紹介。「自然に健康になれる取組みにおいては、企業側にインセンティブを与えるために健康経営の取組みは大事である。また、健康保険の保険者の認知を上げることも重要だ。予防や健康づくりの領域は学術的なエビデンスが少ない領域なので、データを使って貢献していきたい」と述べた。
博報堂DYホールディングスの松本友里上席研究員は、健康経営上の課題として、①無関心な社員を巻き込めない②健診結果のデータが活用しきれていない―の2点を指摘。社員の行動変容を促し、健康経営のPDCAを促すために実施した実証実験の取組みを紹介した。定期健康診断をスポーツの大会になぞらえて「去年の自分のカラダに挑む、健康診断エンターテイメント 健診戦開幕」と告知。前年と比べて健診結果が改善した社員を表彰することで、無関心層や有リスク者を巻き込み、行動変容と健康改善を実現することに成功した。
国立環境研究所の南齋規介資源循環領域国際資源持続性研究室長は、世界の医療需要により年間2.4ギガトンの温室効果ガスが排出されていると説明。G7各国ではヘルスケアシステムの脱炭素化が進められており、日本のヘルスケア産業にも脱炭素化への取組みが求められると指摘した。「炭素排出がヘルスケア経営のリスクとなるような診療報酬や金融制度づくりを先導することが重要である」と提言した。
アストラゼネカ株式会社の濱田琴美執行役員は、再生可能エネルギーの利用など、同社の環境問題への取組みを紹介した。同社では2020年から国内全拠点の使用エネルギーの100%を再生可能エネルギーとした。営業車の電気自動車への切り換えにも取り組んでいることが示された。


